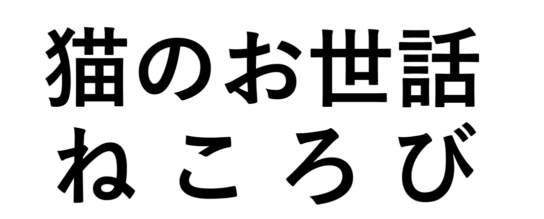こんにちは。お変わりありませんか。
猫事業の合間に、稲の種まきをしました。
種蒔き作業
土を詰めたパレット(育苗箱)に水を十分含ませてから、満遍なく稲の種を蒔きます。
種は籾殻のついたお米。水に浸してひょろっと発芽し始めたもの。
種は殺菌剤で処理されていて直に触れると手が荒れるため、アクリルニトリルの手袋を。
さて、満遍なくといっても板前の塩振りみたいなことしたら種が溢れてしまう。
苗がぎっしり生えるようにしっかり蒔くのは案外難しいの。
その後、手回しコンベアに載せながら、うっすらと土を被せていくのですが、これが5人がかりの流れ作業。
装置に込めると自然に流下する土、コンベアのスピードで厚さが決まるので、
回すハンドルは80代の腰の曲がった神しかいじれないのよ。
そのハンドル捌きに支障を来さないよう、次から次へと育苗箱を差し込んで行かなければならない。テンポ良く。
でも、たっぷり水を含ませた後の土は重いのね、
パレットを並べたときの重さの倍ぐらいに感じる。
中腰で扱い、ひたすら同じ動作を繰り返すものだから、エンドレスな筋トレ(><;)
途中弱音を吐きそうになってしまったけど頑張りました〜。
そして、蒔き終わった育苗箱は並べてビニールシートをかけて成長を促します。
これが育つと、小学校時代の田植えごっこでみたあの苗代になるわけ。
お米づくりの先々
この田んぼも、あと2年ほどで米作り辞めようと思っているとのこと。
80超の神(気安くお婆ちゃんなんて呼べない技術者よ、偉大なる師)が、もう引退したいというのと
この田んぼづくりの技術を受け継いでいる人がいないから。
人件費を含めなくても、かかる経費で赤字なんだそう。
農業設備はとても高価で、メンテナンス費用もかかる。
田んぼがあるからお米を作っているけれども
赤字ではね、
それは現実問題続けられない。
食糧自給率とか、補助だとか、余ってるから減らせとか、米食べろとか、後継者問題とかあっちこっちでいうけども、
フツーの人が簡単には農家になれない仕組みや土地問題や諸々総合して、なるようにしかならんね、とこの頃思います。
何かひとつ頑張ったところでこの流れが変わることはないと思うし、
知れば知るほど軽々しく米は作ったほうがいいとか言えなくなった。
お米つくりたければ、田んぼを貸しますよ、と農家さんがおっしゃっているので
志のある方は、ぜひ。
日本人の米離れっていうけれども
いろいろ調べてみると、そもそも日本人すべてが米だけの飯を食べられるようになったのは、1960年代以降だそうですね。
群馬の農村部はその時代にあっても漬菜とうどんだったと、当時の話として東京から出張した人の昔話できいたことがある。
主食が米というのは、歴史的に短い間のこと。
それに、米って年貢だもんね(明治初期まで米で納税できた)。庶民は食べてないのだわ。
時代のどこを切り出して
米離れ?
というところかと。
日本人の米離れを海外の日本食ブームと併せて論じて、日本人は価値がわかってないって断じているのを見たけど、
まあ・・・そういう面もあるかも?くらいな感じかなあ。
いずれにしても移り変わっていくのは仕方ないのね。
現時点では、欲すればいつでも美味しい白いご飯が食べられるという最高に幸せな環境ですが
永劫継続されるものではないということを噛み締めながら
今あるものを、今目の前に供されたものを残さず食う!
それに尽きる。
さて、お裾分けでいただいた収穫物で、うるいの酢味噌和え、春菊のナムル、曲がり胡瓜の八丁味噌ディップ。それにとっておきのピータン豆腐で夕食です。
うー・・日本酒買っておけばよかったなぁ〜。

そういえば日本酒もお米でできているのだよね・・・・・
9割輸入している蕎麦のように、将来的にはお米も外国から輸入したものを、やっぱ美味いねぇって食べているのかも知れませんね。